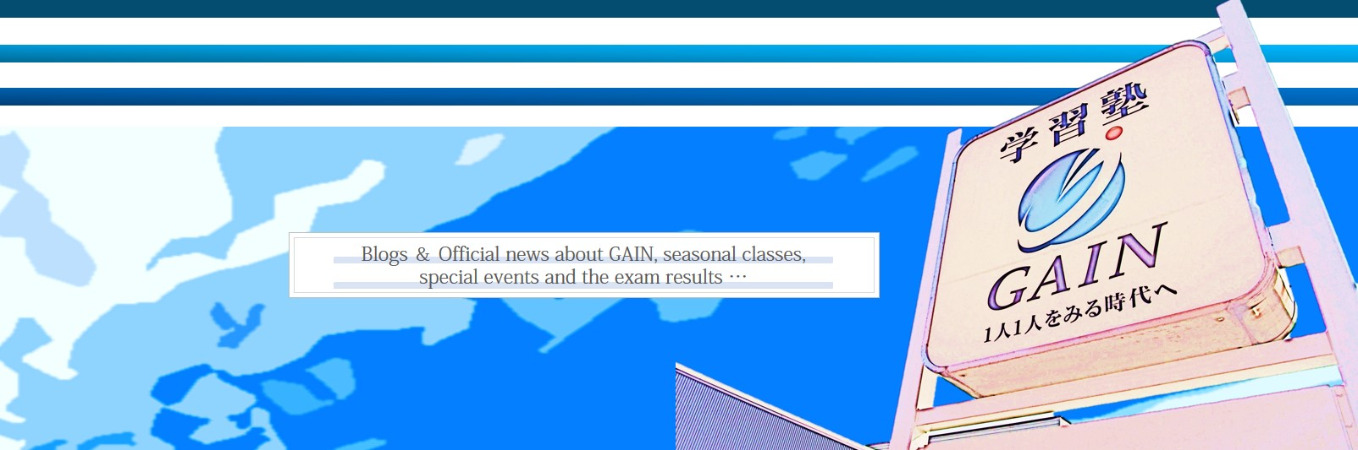みなさんこんにちは、
金沢市・白山市の学習塾、GAINです!
公立高校入試が終わりはや2カ月が経とうとしてます。
5月に入り、石川県教育委員会から公立高校入試の
合格者平均点が発表されました。
去年も投稿したのですが、今年も次の受験生のために
令和6年度入試のまとめを投稿したいと思います。
去年と比べてどのように変わったのか、また今後の変化も考えながら
あくまで個人的な所感をつらつらと書いていきますね。
ご参考になれば嬉しいです(^^♪
合格者平均点
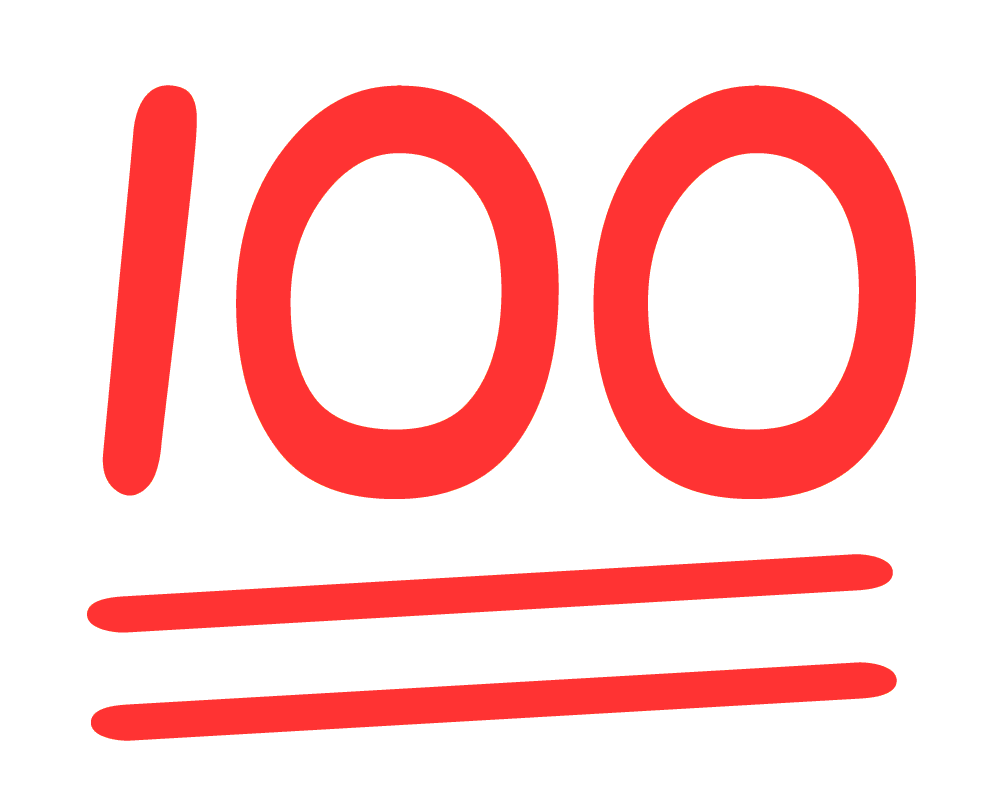
2024年度入試の合格者平均点です。( )は昨年度の平均点となります。
国語・・・67.2点(59.3点)
理科・・・52.0点(50.8点)
英語・・・48.0点(50.2点)
社会・・・41.1点(41.9点)
数学・・・51.1点(44.4点)
合計・・・259点(247点)
以上の結果となりました。
平均点が10点以上上がり、去年に比べ易しめの問題になったようです。
国語・・・67.2点(59.3点)
理科・・・52.0点(50.8点)
英語・・・48.0点(50.2点)
社会・・・41.1点(41.9点)
数学・・・51.1点(44.4点)
合計・・・259点(247点)
以上の結果となりました。
平均点が10点以上上がり、去年に比べ易しめの問題になったようです。
各高校のボーダーライン(予想)

受験生にとって気になるのは、何点取れれば志望校に合格するかだと思います。
もちろんボーダーラインは平均点などによって点数の上下はありますが
今年受験したGAINの生徒から聞いた点数開示での点数を参考にしながら発表していきます。
わかりやすいように平均点と比較してご紹介しますね。数値はおよその点数ですのでご注意を!
泉丘高校(理数)・・・平均+140点
泉丘高校(普通)・・・平均+120点
ニ水高校・・・平均+70点
小松高校(普通)・・・平均+60点
桜丘高校・・・平均+70点
錦丘高校・・・平均+40点
西高校 ・・・平均+15点
明倫高校・・・平均-30点
伏見高校・・・平均-70点
泉丘高校に比べてニ水高校のボーダーが低いことが目立ちますが、一定の人気があるため平均+90点ぐらいを目指しながら勉強することをおすすめします。
また、ニ水高校とボーダーラインが並んだ桜丘高校ですが、一定地域(かほく市や森本)からの受験者が多く、大体を占めるため年によってボーダーが変わりやすいです。
人気があり、倍率も高いため毎年ボーダーラインの予想が難しいですが、ニ水高校に合格できる!という点数で受験すると安心かもしれません。
明倫高校はボーダーラインを平均-30点と記載しましたが、今年の受験では定員割れが起こり、平均-70点ほどの点数でも合格者が出ていました。
ですが、「定員割れだから全員合格!」という認識は捨ててください。実際に今年の加賀地区の高校では定員割れで不合格者が出ています。
反対に定員オーバーで合格者を出している高校もあるみたいです、、(どういうこと?)
とりあえず、定員や倍率に左右されない実力をつければ、どんな受験も怖くない!ということですね(^_-)-☆
ぜひ平均点との差というのを日頃のテストから意識して、受験校決定の目安としてみてくださいね!
もちろんボーダーラインは平均点などによって点数の上下はありますが
今年受験したGAINの生徒から聞いた点数開示での点数を参考にしながら発表していきます。
わかりやすいように平均点と比較してご紹介しますね。数値はおよその点数ですのでご注意を!
泉丘高校(理数)・・・平均+140点
泉丘高校(普通)・・・平均+120点
ニ水高校・・・平均+70点
小松高校(普通)・・・平均+60点
桜丘高校・・・平均+70点
錦丘高校・・・平均+40点
西高校 ・・・平均+15点
明倫高校・・・平均-30点
伏見高校・・・平均-70点
泉丘高校に比べてニ水高校のボーダーが低いことが目立ちますが、一定の人気があるため平均+90点ぐらいを目指しながら勉強することをおすすめします。
また、ニ水高校とボーダーラインが並んだ桜丘高校ですが、一定地域(かほく市や森本)からの受験者が多く、大体を占めるため年によってボーダーが変わりやすいです。
人気があり、倍率も高いため毎年ボーダーラインの予想が難しいですが、ニ水高校に合格できる!という点数で受験すると安心かもしれません。
明倫高校はボーダーラインを平均-30点と記載しましたが、今年の受験では定員割れが起こり、平均-70点ほどの点数でも合格者が出ていました。
ですが、「定員割れだから全員合格!」という認識は捨ててください。実際に今年の加賀地区の高校では定員割れで不合格者が出ています。
反対に定員オーバーで合格者を出している高校もあるみたいです、、(どういうこと?)
とりあえず、定員や倍率に左右されない実力をつければ、どんな受験も怖くない!ということですね(^_-)-☆
ぜひ平均点との差というのを日頃のテストから意識して、受験校決定の目安としてみてくださいね!
各教科分析
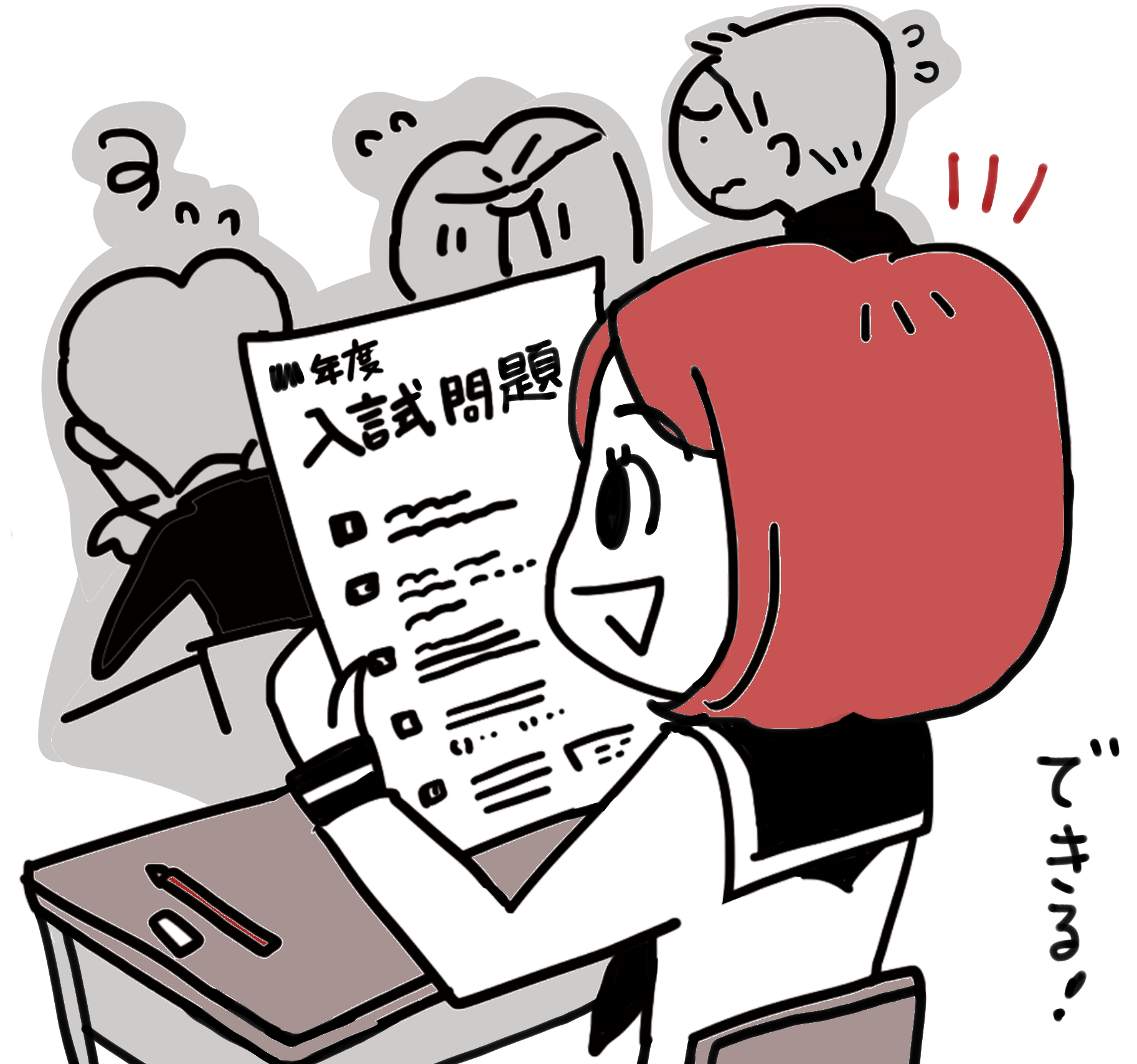
今年度の入試を分析し、変化などがあればご紹介します。
また、受験に向けてどのような勉強が必要か、意識すること、などなど
少しでも受験のためになることをお伝えできればと思います!
また、受験に向けてどのような勉強が必要か、意識すること、などなど
少しでも受験のためになることをお伝えできればと思います!
国語
国語の問題構成は以下の通りです。
大問1 漢字
大問2 物語文
大問3 評論文
大問4 古典
大問5 作文
この形式は令和になって以来ほとんど変化がありません。
さて、国語の受験対策を始めるにあたって、まず一番初めに伝えなければならないことがあります。それは、、
国語は一番時間配分をミスりやすい!!!ということです。
5教科の中で一番時間が足りなくなる科目は国語と言い切ります。
そうなる要素はいくつか考えられます。
例えば、思考力を求められる問題が多いこと(他の科目は知識の活用力を活かす問題が多い)、記述量が多いこと、そしてやばいのが一番最初の科目ということ、、、です。
受験の雰囲気にのまれて頭が真っ白になる恐れがあります。
だからこそ時間計測がキーワードとなります。普段の学習から時間計測を行い、また目標解答時間を短めに設定して負荷をかけていきましょう。
国語の点数の取り方、勉強の優先順位は
1.漢字 2.選択問題 3.抜き出し問題 4.古典 5.作文 6.記述問題 です!また、記述は完答ではなく途中点を狙うことを意識して解くことをおすすめします!空欄はダメ!もったいない!!
日々の勉強でも意識してくださいね~
大問1 漢字
大問2 物語文
大問3 評論文
大問4 古典
大問5 作文
この形式は令和になって以来ほとんど変化がありません。
さて、国語の受験対策を始めるにあたって、まず一番初めに伝えなければならないことがあります。それは、、
国語は一番時間配分をミスりやすい!!!ということです。
5教科の中で一番時間が足りなくなる科目は国語と言い切ります。
そうなる要素はいくつか考えられます。
例えば、思考力を求められる問題が多いこと(他の科目は知識の活用力を活かす問題が多い)、記述量が多いこと、そしてやばいのが一番最初の科目ということ、、、です。
受験の雰囲気にのまれて頭が真っ白になる恐れがあります。
だからこそ時間計測がキーワードとなります。普段の学習から時間計測を行い、また目標解答時間を短めに設定して負荷をかけていきましょう。
国語の点数の取り方、勉強の優先順位は
1.漢字 2.選択問題 3.抜き出し問題 4.古典 5.作文 6.記述問題 です!また、記述は完答ではなく途中点を狙うことを意識して解くことをおすすめします!空欄はダメ!もったいない!!
日々の勉強でも意識してくださいね~
理科
理科の問題形式は
大問1 小問集合
大問2 生物
大問3 化学
大問4 物理
大問5 地学
大問6 融合問題
と今年の入試ではなりましたが、大問2~5は生物、化学、物理、地学がランダムに配置されるので注意が必要です。
今年は生物は中2内容、化学は中3内容、物理は中1内容、地学は中3内容が出題されました。毎年どれも配点が16~18点ほどでバランスに大きな隔たりはありません。
理科の入試対策の手段としてよく挙げられるのが「暗記」ですが、もうこの時代は終わっています、、。もちろんすべての勉強において暗記はスタートになることですが、それだけでは平均点にすら到達しないでしょう。
今からは「なぜ」を説明できるように原理原則を理解する勉強に切り替えましょう!
また、配点を見て分かるように理科はすべての分野がバランスよく出題されるので、山をはるなんてことはせず、どの分野がでても答えられるように勉強しましょう。ただし、理科が本当に苦手な人に関しては、「生物」「地学」の分野から勉強することをおすすめします。なぜなら計算単元が少なく、用語を覚える単元が「物理」「化学」に比べて多いからです。繰り返しますが、その分野だけ勉強していてはダメですよ!
大問1 小問集合
大問2 生物
大問3 化学
大問4 物理
大問5 地学
大問6 融合問題
と今年の入試ではなりましたが、大問2~5は生物、化学、物理、地学がランダムに配置されるので注意が必要です。
今年は生物は中2内容、化学は中3内容、物理は中1内容、地学は中3内容が出題されました。毎年どれも配点が16~18点ほどでバランスに大きな隔たりはありません。
理科の入試対策の手段としてよく挙げられるのが「暗記」ですが、もうこの時代は終わっています、、。もちろんすべての勉強において暗記はスタートになることですが、それだけでは平均点にすら到達しないでしょう。
今からは「なぜ」を説明できるように原理原則を理解する勉強に切り替えましょう!
また、配点を見て分かるように理科はすべての分野がバランスよく出題されるので、山をはるなんてことはせず、どの分野がでても答えられるように勉強しましょう。ただし、理科が本当に苦手な人に関しては、「生物」「地学」の分野から勉強することをおすすめします。なぜなら計算単元が少なく、用語を覚える単元が「物理」「化学」に比べて多いからです。繰り返しますが、その分野だけ勉強していてはダメですよ!
英語
今年の英語の問題構成は
大問1 リスニング
大問2 並び替え、適文補充
大問3 対話文読解
大問4 長文読解
となりました。大問2では問題傾向が変わりやすく、過去問にはなかった傾向の問題が出て焦った人もいるかと思いますが、難易度は高くなかったので、落ち着いて解答した人はばっちりだったと思います。
文法や単語をきっちり勉強していれば、どのような形式の問題が出たとしても戸惑わず実力を発揮できるので、英語の対策はそこを軸に取り組みましょう。
英語の問題で一番注意すべきは大問3と4の長文問題です。落ち着いて読むことができれば解ける問題も多いですが、なんせ時間は50分と限られています。しかもリスニングに強制的に時間を取られるわけですから、残りの解答時間は40分弱です。
だからこそ、長文読解のトレーニングは必須となります。GAINでも秋に長文読解コースができ、そこで毎日長文トレーニングを実施します。「速く」と「正確に」を両立できるように取り組み、受験に向かうことが戦略のカギとなります。
長文が苦手と言う人はまず、時間がかかってもいいので正確に読むというトレーニングから始めましょう。正確に読むためには単語知識も必要なのでコツコツが大切です。正確に読めるようになってくると自然と速く読めるようになります。この順序を逆転させてしまうと苦労するので気を付けてください。
また、長文と同様に英作文を苦手とする人も多いと思います。英作文は「型」が重要です。自分が得意な英語のフレーズをいくつか用意しておけば、あとはテーマに合わせて当てはめていくだけで大丈夫です。全ての教科の記述問題は途中点を稼ぐ気持ちで挑みましょう!
大問1 リスニング
大問2 並び替え、適文補充
大問3 対話文読解
大問4 長文読解
となりました。大問2では問題傾向が変わりやすく、過去問にはなかった傾向の問題が出て焦った人もいるかと思いますが、難易度は高くなかったので、落ち着いて解答した人はばっちりだったと思います。
文法や単語をきっちり勉強していれば、どのような形式の問題が出たとしても戸惑わず実力を発揮できるので、英語の対策はそこを軸に取り組みましょう。
英語の問題で一番注意すべきは大問3と4の長文問題です。落ち着いて読むことができれば解ける問題も多いですが、なんせ時間は50分と限られています。しかもリスニングに強制的に時間を取られるわけですから、残りの解答時間は40分弱です。
だからこそ、長文読解のトレーニングは必須となります。GAINでも秋に長文読解コースができ、そこで毎日長文トレーニングを実施します。「速く」と「正確に」を両立できるように取り組み、受験に向かうことが戦略のカギとなります。
長文が苦手と言う人はまず、時間がかかってもいいので正確に読むというトレーニングから始めましょう。正確に読むためには単語知識も必要なのでコツコツが大切です。正確に読めるようになってくると自然と速く読めるようになります。この順序を逆転させてしまうと苦労するので気を付けてください。
また、長文と同様に英作文を苦手とする人も多いと思います。英作文は「型」が重要です。自分が得意な英語のフレーズをいくつか用意しておけば、あとはテーマに合わせて当てはめていくだけで大丈夫です。全ての教科の記述問題は途中点を稼ぐ気持ちで挑みましょう!
社会
社会は以下のように出題されました。
大問1 世界地理
大問2 歴史
大問3 公民
大問4 日本地理
大問5 歴史
大問6 公民
社会は5教科の中でも平均点が低く、多くの生徒が苦戦する科目です。大問1,4は地理の問題が出題されますが、図表などの資料が多く記載されています。よくある問題は複数の資料が出されて、その複数の資料を関連させて読み取る問題です。このような場合は必ず設問条件に則って、片方の資料だけ見るのではなく2つの資料のことについて答えるように意識しましょう。
お次、大問2、5は歴史の分野です。歴史は時代ごとの出来事や人物を覚える勉強をしているかと思います。ですが、実際の入試問題では「時代を超えて」出題されます。「テーマ史」というものがあり、ひとつのテーマに絞って書く時代の特徴を問われる問題があります。「文化」「国際社会との関わり」「政治」「戦争」「交易」などがテーマとして挙げられ年表とともに出題されます。
各時代を区別して覚えている人は「テーマ」で切り取って各時代を比較するような勉強もしてみてください。
そして大問3、6は公民です。公民は中3になって習い始めるため、受験知識としては比較的新しい単元となります。習いたての単元であるため、復習もスムーズにすすむと思います。しかしデメリットもあります。それは、入試演習をする時間が足りないということです。学校のカリキュラムでは入試ギリギリにならないと単元修了とならないため、予習ベースで進めることをおすすめします。
社会はすべて分野がまんべんなく出題され、配点もおなじくらいなのでバランスよく勉強することが大切です。歴史や地理は復習する範囲が広いため、最初から復習をスタートさせる人も多いですが、優先順位をつけて自分の苦手なところからコツコツ復習を始めましょう。
また、社会は記述問題が非常に多く、「なぜ」を理解していないと答えられる問題に限界があります。それを理解できて初めて記述問題の練習ができます。
やることが多く感じますが、一つずつ丁寧に取り組んでいきましょう!
大問1 世界地理
大問2 歴史
大問3 公民
大問4 日本地理
大問5 歴史
大問6 公民
社会は5教科の中でも平均点が低く、多くの生徒が苦戦する科目です。大問1,4は地理の問題が出題されますが、図表などの資料が多く記載されています。よくある問題は複数の資料が出されて、その複数の資料を関連させて読み取る問題です。このような場合は必ず設問条件に則って、片方の資料だけ見るのではなく2つの資料のことについて答えるように意識しましょう。
お次、大問2、5は歴史の分野です。歴史は時代ごとの出来事や人物を覚える勉強をしているかと思います。ですが、実際の入試問題では「時代を超えて」出題されます。「テーマ史」というものがあり、ひとつのテーマに絞って書く時代の特徴を問われる問題があります。「文化」「国際社会との関わり」「政治」「戦争」「交易」などがテーマとして挙げられ年表とともに出題されます。
各時代を区別して覚えている人は「テーマ」で切り取って各時代を比較するような勉強もしてみてください。
そして大問3、6は公民です。公民は中3になって習い始めるため、受験知識としては比較的新しい単元となります。習いたての単元であるため、復習もスムーズにすすむと思います。しかしデメリットもあります。それは、入試演習をする時間が足りないということです。学校のカリキュラムでは入試ギリギリにならないと単元修了とならないため、予習ベースで進めることをおすすめします。
社会はすべて分野がまんべんなく出題され、配点もおなじくらいなのでバランスよく勉強することが大切です。歴史や地理は復習する範囲が広いため、最初から復習をスタートさせる人も多いですが、優先順位をつけて自分の苦手なところからコツコツ復習を始めましょう。
また、社会は記述問題が非常に多く、「なぜ」を理解していないと答えられる問題に限界があります。それを理解できて初めて記述問題の練習ができます。
やることが多く感じますが、一つずつ丁寧に取り組んでいきましょう!
数学
問題数は大きな変化はなく、
大問1 小問集合
大問2 統計
大問3 関数(1次関数)
大問4 方程式
大問5 作図
大問6 平面図形
大問7 空間図形
という問題構成となりました。
数学は5教科の中でも難しいという位置づけでしたが
ここ数年は易しい問題も増えたイメージです。
ただし、試験時間内に解くといった意味では受験生にとっては
大きな障害となる科目に間違いありません。
数学が苦手な人は大問1の小問集合で確実に点数をとることや各大問の(1)を解く力を身につけることが大切です。どれも学校の定期テストレベルの対策で十分に点数をとることができます。
数学が得意!という人はぜひ他の人と差をつけたいですよね。
その場合、石川県の問題では図形の問題で差をつけやすいです。
一見難しそうに見える問題でも挑戦してみると解けるというパターンが最近の問題には多いようです。後回しにせずトライしてみてください!
大問1 小問集合
大問2 統計
大問3 関数(1次関数)
大問4 方程式
大問5 作図
大問6 平面図形
大問7 空間図形
という問題構成となりました。
数学は5教科の中でも難しいという位置づけでしたが
ここ数年は易しい問題も増えたイメージです。
ただし、試験時間内に解くといった意味では受験生にとっては
大きな障害となる科目に間違いありません。
数学が苦手な人は大問1の小問集合で確実に点数をとることや各大問の(1)を解く力を身につけることが大切です。どれも学校の定期テストレベルの対策で十分に点数をとることができます。
数学が得意!という人はぜひ他の人と差をつけたいですよね。
その場合、石川県の問題では図形の問題で差をつけやすいです。
一見難しそうに見える問題でも挑戦してみると解けるというパターンが最近の問題には多いようです。後回しにせずトライしてみてください!
最後に

以上が2024年度公立高校入試の分析でした。
石川県の公立高校入試は思考力を問われる問題が非常に多く出題され、全国的にみてもレベルが高い問題設定となっています。
中学1、2年生が学校のテストを中心に知識に抜けがないか常に確認し、苦手をそのままにしないよう心がけましょう。
中学3年生は新しい単元の習得と並行して1,2年の復習を開始していってください。
今までに習った範囲は受験レベルまで引き上げる必要があるので、すでに受験勉強をスタートさせましょう。
時間は有限です。どのように時間を使っていくかで最終的な結果は大きく変わります。
GAINでも最大限のサポートをしますので、自分の目標に向かってともに頑張っていきましょう!!
ぜひ分析結果を参考にこれからの勉強に取り組んでくださいね!(^^)!
石川県の公立高校入試は思考力を問われる問題が非常に多く出題され、全国的にみてもレベルが高い問題設定となっています。
中学1、2年生が学校のテストを中心に知識に抜けがないか常に確認し、苦手をそのままにしないよう心がけましょう。
中学3年生は新しい単元の習得と並行して1,2年の復習を開始していってください。
今までに習った範囲は受験レベルまで引き上げる必要があるので、すでに受験勉強をスタートさせましょう。
時間は有限です。どのように時間を使っていくかで最終的な結果は大きく変わります。
GAINでも最大限のサポートをしますので、自分の目標に向かってともに頑張っていきましょう!!
ぜひ分析結果を参考にこれからの勉強に取り組んでくださいね!(^^)!