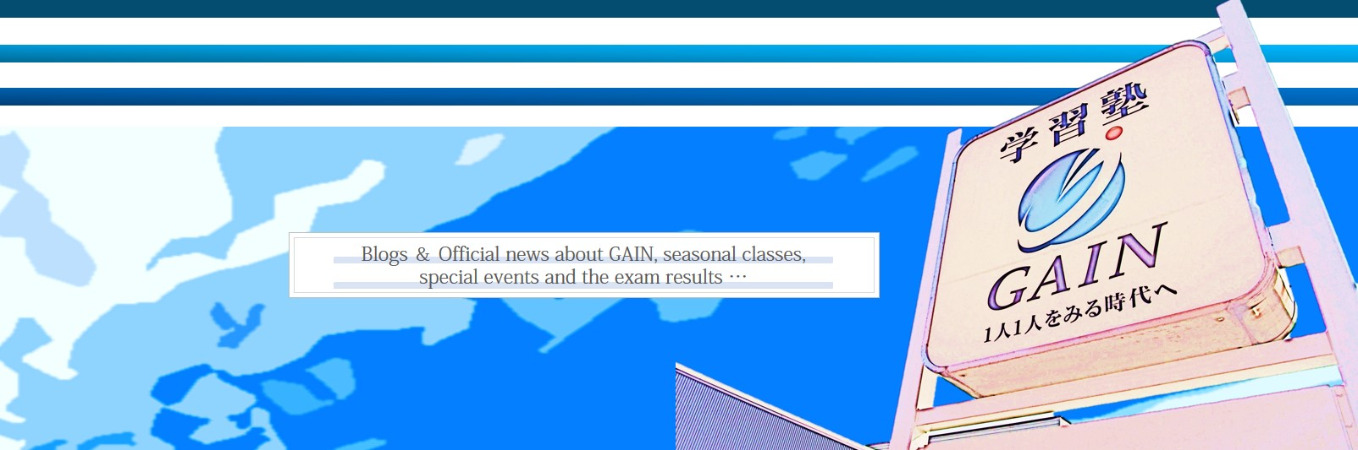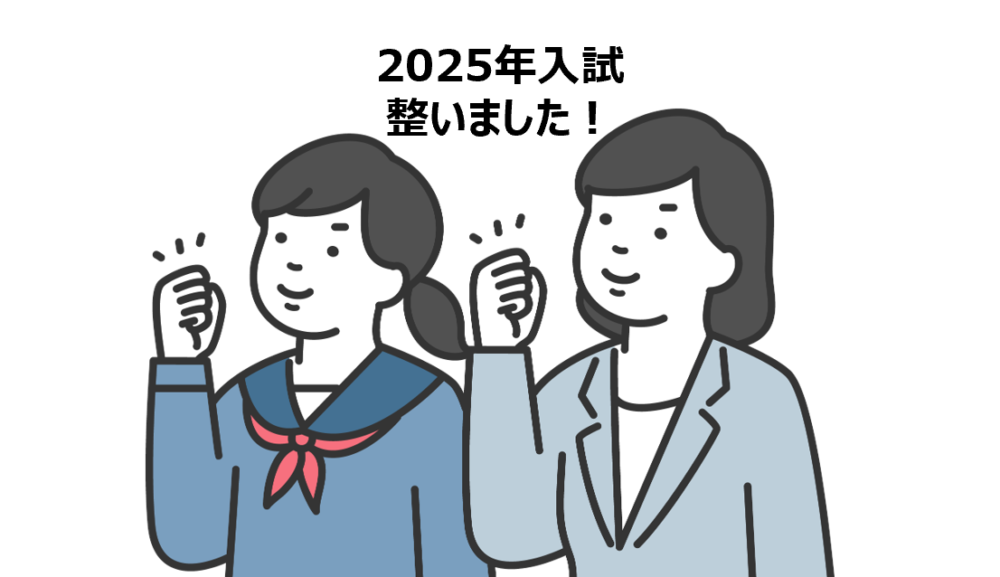みなさんこんにちは!
金沢市・白山市の学習塾、GAINです
今年も石川県教育委員会から公立高校入試の
合格者平均点が発表されました!
そこで、、入試分析やっちゃいますよ~~
特に受験を控える中学生の方々はぜひ参考にして
自分の受験勉強に役立ててほしいと思います(^^)/
合格者平均点
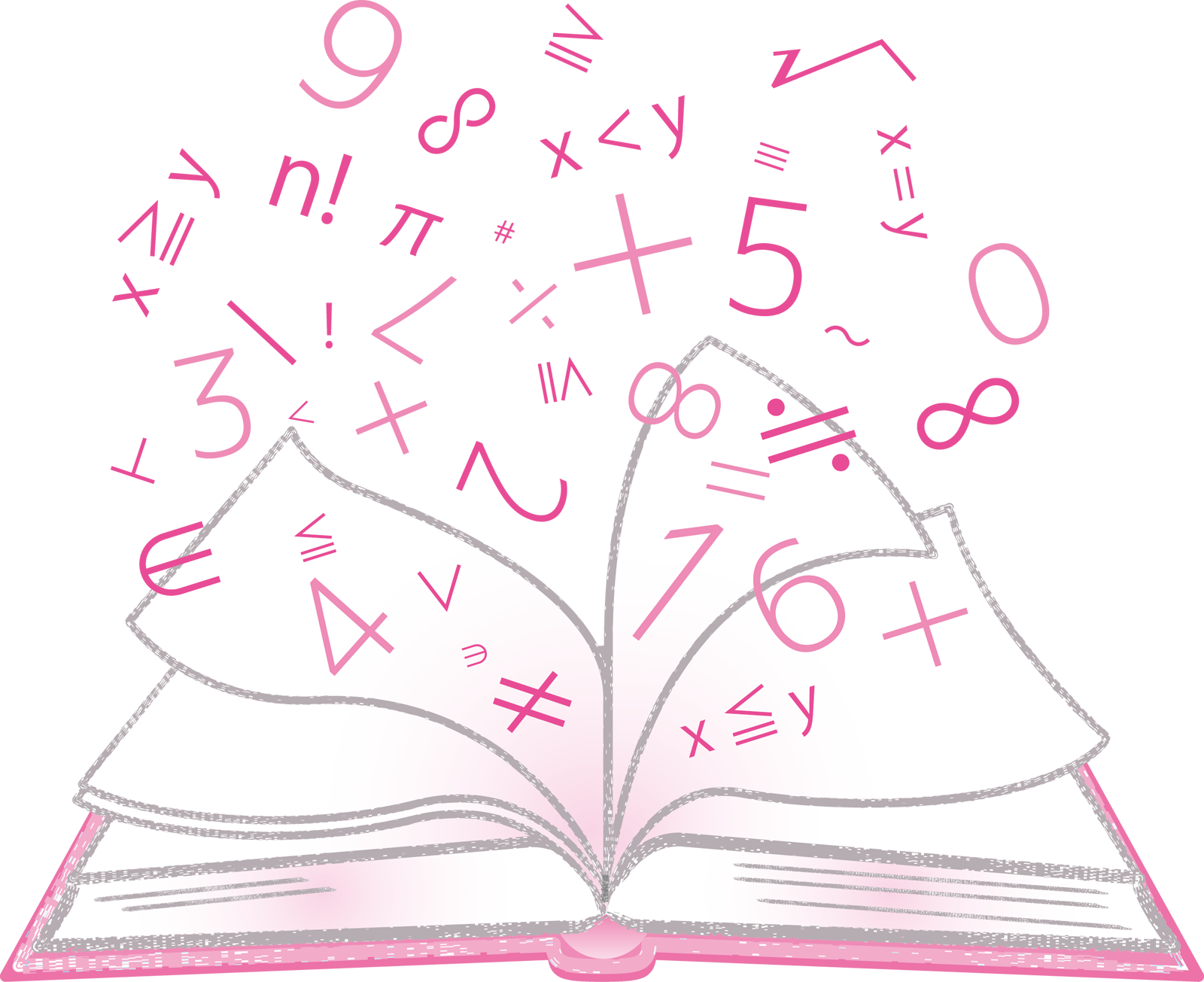
2025年入試の合格者平均点は以下の通りです!※( )は昨年の平均点
国語・・・54.7点 (67.2点) 昨年比-12.5点
理科・・・47.4点 (52.0点) 昨年比-4.6点
英語・・・51.6点 (48.0点) 昨年比+3.6点
社会・・・46.3点 (41.1点) 昨年比+5.2点
数学・・・46.9点 (51.1点) 昨年比-4.2点
合計・・・247点(259点)
昨年の入試は科目間の平均点に偏りが出ましたが
今年の入試は大きな偏りがなくバランスの良い点数ですね。
全体の平均点は昨年より10点以上下がり、2023年の入試と同じ点数となりました!
国語・・・54.7点 (67.2点) 昨年比-12.5点
理科・・・47.4点 (52.0点) 昨年比-4.6点
英語・・・51.6点 (48.0点) 昨年比+3.6点
社会・・・46.3点 (41.1点) 昨年比+5.2点
数学・・・46.9点 (51.1点) 昨年比-4.2点
合計・・・247点(259点)
昨年の入試は科目間の平均点に偏りが出ましたが
今年の入試は大きな偏りがなくバランスの良い点数ですね。
全体の平均点は昨年より10点以上下がり、2023年の入試と同じ点数となりました!
各高校のボーダーライン(予想)
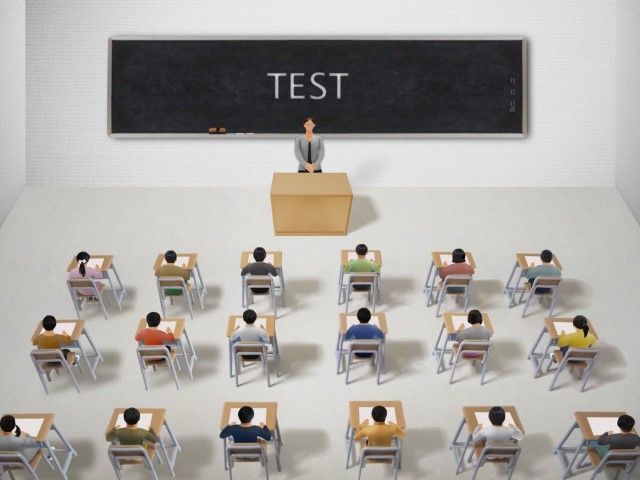
さて、お次はみなさま気になるボーダーラインですね。
毎年注意喚起してますが、ボーダーラインは平均点によって上下しますので
今年の入試をもとに、そしてGAINの生徒から聞いた点数を参考し発表していきます。
数値はおよその点数ですので、ご注意あれ!
泉丘高校(理数)・・・平均+150点(ボーダー約400点)
泉丘高校(普通)・・・平均+115点(ボーダー約360点)
ニ水高校 ・・・平均+80点(ボーダー約325点)
小松高校(理数)・・・平均+100点(ボーダー約350点)
小松高校(普通)・・・平均+50点(ボーダー約300点)
桜丘高校 ・・・平均+70点(ボーダー約320点)
錦丘高校 ・・・平均+40点(ボーダー約285点)
西高校 ・・・平均-7点(ボーダー240点)
明倫高校 ・・・平均-20点(ボーダー220点)
伏見高校 ・・・平均-80点(ボーダー170点)
※コースや学科によって異なる高校は省略しております(..)
泉丘高校は理数科、普通科ともにボーダーラインの大きな変動は起きてません。
ニ水高校に関しては前回より少しだけボーダーラインが上昇した印象を受けます。
小松高校の普通科は倍率が昨年より下がったのが原因なのかボーダーラインが下がってる可能性あります。
他にも金沢西のボーダーラインは今年は低い印象です。平均点以上のイメージが強かったですが、、
もちろん、これよりも低い点数でも合格している人はいると思いますし、石川県の入試は内申点も加味されますから
入試の点数で下剋上が起きているケースもあります!!
ただ、圧倒的点数をたたき出していれば、そのような下剋上に巻き込まれることはないので
もし1,2年生の時の成績に自信がない、、という人でも入試の点数で挽回できる余地はたくさんあります。
ただし、、これを見ている1,2年生は今のうちから内申点を意識して勉強することに越したことはないので
いまからコツコツ頑張っていきましょう~。
毎年注意喚起してますが、ボーダーラインは平均点によって上下しますので
今年の入試をもとに、そしてGAINの生徒から聞いた点数を参考し発表していきます。
数値はおよその点数ですので、ご注意あれ!
泉丘高校(理数)・・・平均+150点(ボーダー約400点)
泉丘高校(普通)・・・平均+115点(ボーダー約360点)
ニ水高校 ・・・平均+80点(ボーダー約325点)
小松高校(理数)・・・平均+100点(ボーダー約350点)
小松高校(普通)・・・平均+50点(ボーダー約300点)
桜丘高校 ・・・平均+70点(ボーダー約320点)
錦丘高校 ・・・平均+40点(ボーダー約285点)
西高校 ・・・平均-7点(ボーダー240点)
明倫高校 ・・・平均-20点(ボーダー220点)
伏見高校 ・・・平均-80点(ボーダー170点)
※コースや学科によって異なる高校は省略しております(..)
泉丘高校は理数科、普通科ともにボーダーラインの大きな変動は起きてません。
ニ水高校に関しては前回より少しだけボーダーラインが上昇した印象を受けます。
小松高校の普通科は倍率が昨年より下がったのが原因なのかボーダーラインが下がってる可能性あります。
他にも金沢西のボーダーラインは今年は低い印象です。平均点以上のイメージが強かったですが、、
もちろん、これよりも低い点数でも合格している人はいると思いますし、石川県の入試は内申点も加味されますから
入試の点数で下剋上が起きているケースもあります!!
ただ、圧倒的点数をたたき出していれば、そのような下剋上に巻き込まれることはないので
もし1,2年生の時の成績に自信がない、、という人でも入試の点数で挽回できる余地はたくさんあります。
ただし、、これを見ている1,2年生は今のうちから内申点を意識して勉強することに越したことはないので
いまからコツコツ頑張っていきましょう~。
各教科分析
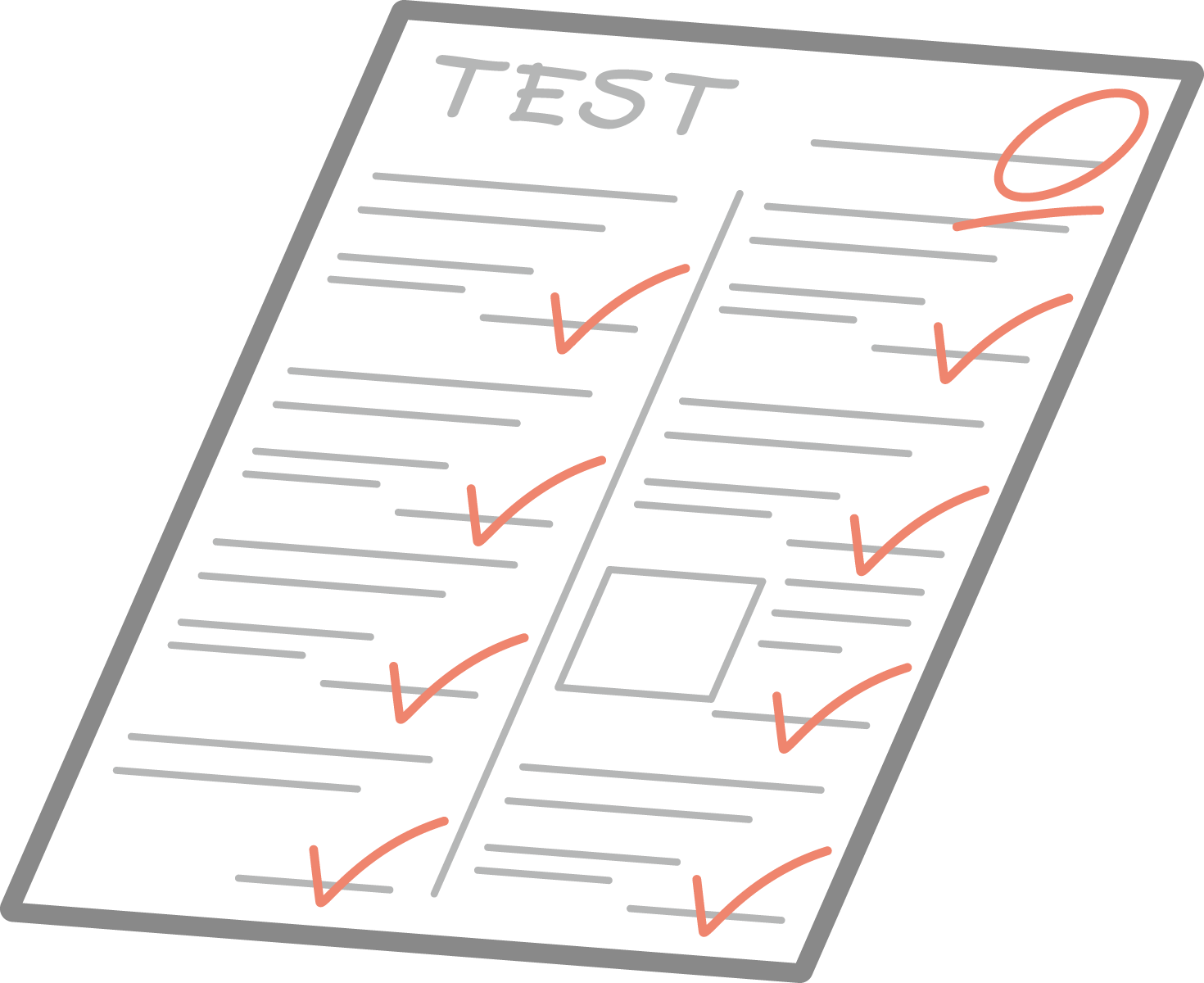
では、2025年の入試分析にはいります。
昨年からの変化についてお伝えできればと思います。
また、受験に向けて何を勉強すればいいのか分からない、何を優先すべき?と悩んでいる人も少なくないはずなので
少しでも受験勉強のためになることをお伝えできるよう努めますね~
昨年からの変化についてお伝えできればと思います。
また、受験に向けて何を勉強すればいいのか分からない、何を優先すべき?と悩んでいる人も少なくないはずなので
少しでも受験勉強のためになることをお伝えできるよう努めますね~
国語
国語の問題構成は以下の通りです。( )は配点です。
大問1 漢字(16点)
大問2 物語(29点)
大問3 論説(30点)
大問4 古文(15点)
大問5 作文(10点)
生徒は難しかった、、、と受験後にこぼしていましたが全体的に無難な問題が多く
総合模試より簡単だったんじゃないかと思っています。
平均点が下がったのは、おそらく昨年も問題が易しすぎただけだと思うので
これくらいのレベルを想定して勉強することをおすすめします。
各大問ごとに見ていきます!
大問1「漢字」
うーーーん、ちょっと迷いそうだなと思う問題もありましたが
学校ワークや定期テストレベルだったので、問題ないかと。
読みの問題のほうが難しくなる傾向があるため、見慣れない漢字でも読めるようにしておきましょう。
大問2「物語」
江戸時代のお話でした。時代設定が現代でないと急に生徒は読みにくいと感じます。
GAINの生徒も授業中にひーひー言ってた印象です笑
漢字に関する知識問題が出てきました。これは珍しい。
他にも慣用表現、文法と知識問題がちらほら出題されていたので
「文章を読むのが苦手、、」と思っている人はまずは語句などの知識をつける勉強から始めると点数もある程度とれるようになりますし、その後の読解にも活きそうですね。
国語の勉強においても「知識」は非常に重要です。
例えば、今回の時代設定が江戸時代でしたが、その当時の「当たり前」いわゆる「文化」を知らなければ、「心情」を読み取るのは難しいかもしれません。
このように、様々な体験をして知識を得た生徒は物語の読解に長けていると感じます。
大問3「論説」
指示語、接続語、空欄補充とどれもこれもGAINの授業で行ったことばかり(..)
ですが、少々問題が難しかったと思います。
論説の問題と解くにあたって生徒によく伝えていることは
「話の流れ」をつかもうと意識して!ということです。
物語はストーリーがあるので、読み終えた後にどのような話だったかはインプットされがちですが
論説文を読む際、多くの生徒はただ文字を追っているだけになってます、、
それに気づいて意識を変えるだけで、国語の点数はみるみる上がっていきますよ!!
あとは問題に対する答え方の練習をしていけば完璧ですね('◇')ゞ
大問4「古文」
今年も漢文ではなく、古文でしたね!予想的中!
GAINの授業ではもっと難しい文章に触れていたので多くの生徒は簡単だったと感じているのでは??
古文が出題されたとき、ほぼ必ず問1には現代仮名遣いの問題が出ます。これは確実にとりましょう。
そして毎年おなじみの空欄補充問題。これも総合模試で嫌というほど解いてきたので問題ないかと思います。
ただ、文章全体をしっかり把握していないと解けないようになっているので、古文を読む時間を確保できるような時間配分、解く順番が重要です。
大問5「作文」
ポスターの問題でした。よくある問題ですね。
落ち着いて書けば、満点間違いなしの問題設定でしたが、時間配分や解く順番をミスってしまうと大幅に点数を落としてしまいかねません。
誰でも書けるようなテーマだからこそ、最後までしっかり書ききることができなかった人は相当痛手ですね、、
大問1 漢字(16点)
大問2 物語(29点)
大問3 論説(30点)
大問4 古文(15点)
大問5 作文(10点)
生徒は難しかった、、、と受験後にこぼしていましたが全体的に無難な問題が多く
総合模試より簡単だったんじゃないかと思っています。
平均点が下がったのは、おそらく昨年も問題が易しすぎただけだと思うので
これくらいのレベルを想定して勉強することをおすすめします。
各大問ごとに見ていきます!
大問1「漢字」
うーーーん、ちょっと迷いそうだなと思う問題もありましたが
学校ワークや定期テストレベルだったので、問題ないかと。
読みの問題のほうが難しくなる傾向があるため、見慣れない漢字でも読めるようにしておきましょう。
大問2「物語」
江戸時代のお話でした。時代設定が現代でないと急に生徒は読みにくいと感じます。
GAINの生徒も授業中にひーひー言ってた印象です笑
漢字に関する知識問題が出てきました。これは珍しい。
他にも慣用表現、文法と知識問題がちらほら出題されていたので
「文章を読むのが苦手、、」と思っている人はまずは語句などの知識をつける勉強から始めると点数もある程度とれるようになりますし、その後の読解にも活きそうですね。
国語の勉強においても「知識」は非常に重要です。
例えば、今回の時代設定が江戸時代でしたが、その当時の「当たり前」いわゆる「文化」を知らなければ、「心情」を読み取るのは難しいかもしれません。
このように、様々な体験をして知識を得た生徒は物語の読解に長けていると感じます。
大問3「論説」
指示語、接続語、空欄補充とどれもこれもGAINの授業で行ったことばかり(..)
ですが、少々問題が難しかったと思います。
論説の問題と解くにあたって生徒によく伝えていることは
「話の流れ」をつかもうと意識して!ということです。
物語はストーリーがあるので、読み終えた後にどのような話だったかはインプットされがちですが
論説文を読む際、多くの生徒はただ文字を追っているだけになってます、、
それに気づいて意識を変えるだけで、国語の点数はみるみる上がっていきますよ!!
あとは問題に対する答え方の練習をしていけば完璧ですね('◇')ゞ
大問4「古文」
今年も漢文ではなく、古文でしたね!予想的中!
GAINの授業ではもっと難しい文章に触れていたので多くの生徒は簡単だったと感じているのでは??
古文が出題されたとき、ほぼ必ず問1には現代仮名遣いの問題が出ます。これは確実にとりましょう。
そして毎年おなじみの空欄補充問題。これも総合模試で嫌というほど解いてきたので問題ないかと思います。
ただ、文章全体をしっかり把握していないと解けないようになっているので、古文を読む時間を確保できるような時間配分、解く順番が重要です。
大問5「作文」
ポスターの問題でした。よくある問題ですね。
落ち着いて書けば、満点間違いなしの問題設定でしたが、時間配分や解く順番をミスってしまうと大幅に点数を落としてしまいかねません。
誰でも書けるようなテーマだからこそ、最後までしっかり書ききることができなかった人は相当痛手ですね、、
理科
理科の問題構成は以下の通りです。( )は配点です。
大問1 小問(28点)
大問2 化学(19点)
大問3 生物(17点)
大問4 物理(19点)
大問5 地学(17点)
大きな変更点は、問題形式です!
従来は大問6構成だったのですが、大問1の小問集合に包括されたようです。そのため大問1が拡張されて28点分も配点がありました。他の大問は例年通り、生物、化学、物理、地学がランダムに一律に配置されました。
今年は生物、化学、地学が中1内容、物理が中2内容となりました。
中3の内容は??と思う人もいるかと思いますがしっかり大問1の小問集合で広く中3内容の基礎知識が出題されております。
では、理科の問題を攻略するためのポイントを3つ紹介しますね!
その①:小問集合の徹底対策
大問1の問題が拡張されたことも影響していますが、中1~3年の各分野でバランスよく基礎を習得することが何よりも大切です。
1問1答形式で知識を蓄え、その他大問の点数アップに役立てていきましょう。
その②:実験形式に慣れる
今年の出題傾向のもう1つのトピックとして、大問2,3,4がすべて実験を絡めた出題になっていることが挙げられます。
この形式を攻略するには、ただ演習するだけではうまくいきません。
問題文の読み方、表の使い方をまず理解したうえで演習することを強くお勧めします!
学校の教科書に載っている実験内容を一通り確認するのも非常に良い勉強です!
その③:計算・記述対策は念入りに
例年通りですが、理科で平均点以上とる事を目標とする人は、知識を詰め込むだけではだめです、、
その知識を応用して記述する力や、計算に利用して答えを導き出す練習も必ず行っていきましょう。
特に化学・物理分野は深掘りした理解が重要になってきます。
大問1 小問(28点)
大問2 化学(19点)
大問3 生物(17点)
大問4 物理(19点)
大問5 地学(17点)
大きな変更点は、問題形式です!
従来は大問6構成だったのですが、大問1の小問集合に包括されたようです。そのため大問1が拡張されて28点分も配点がありました。他の大問は例年通り、生物、化学、物理、地学がランダムに一律に配置されました。
今年は生物、化学、地学が中1内容、物理が中2内容となりました。
中3の内容は??と思う人もいるかと思いますがしっかり大問1の小問集合で広く中3内容の基礎知識が出題されております。
では、理科の問題を攻略するためのポイントを3つ紹介しますね!
その①:小問集合の徹底対策
大問1の問題が拡張されたことも影響していますが、中1~3年の各分野でバランスよく基礎を習得することが何よりも大切です。
1問1答形式で知識を蓄え、その他大問の点数アップに役立てていきましょう。
その②:実験形式に慣れる
今年の出題傾向のもう1つのトピックとして、大問2,3,4がすべて実験を絡めた出題になっていることが挙げられます。
この形式を攻略するには、ただ演習するだけではうまくいきません。
問題文の読み方、表の使い方をまず理解したうえで演習することを強くお勧めします!
学校の教科書に載っている実験内容を一通り確認するのも非常に良い勉強です!
その③:計算・記述対策は念入りに
例年通りですが、理科で平均点以上とる事を目標とする人は、知識を詰め込むだけではだめです、、
その知識を応用して記述する力や、計算に利用して答えを導き出す練習も必ず行っていきましょう。
特に化学・物理分野は深掘りした理解が重要になってきます。
英語
英語の問題構成は以下の通りです。( )は配点です。
大問1 リスニング (30点)
大問2 並び替え、適文補充(12点)
大問3 対話文読解 (28点)
大問4 長文読解 (30点)
大きな変更点は特になく、昨年同様の問題構成でした。
では、各大問の分析にまいります!
大問1「リスニング」
リスニングだけで30点も!!!
リスニングというのは不思議なもので、読めても聞き取れないんですよね、、
聞き取れるようにするためには、英語の音声を聞く習慣をつけるしかないです。
GAINの生徒は中3の秋ごろに「長文読解講座」なるものを受講し、読むスピードを上げるだけでなく、聞き取る練習も行います!
また、リスニング教材もあるので、毎日コツコツ積み上げることも可能です!
大問2「並び替え、適文補充」
並ぶ替え問題は英文の構造を理解できているかどうか、つまり文法力を確かめる問題です。
単語だけ覚えていても、太刀打ちできません。
単語とともに文法もきっちり勉強していれば、どのような問題が出ても対応できます!
並び替えが苦手な人は、苦手単元の文法ルールを確認してみて!
大問3「対話文読解」
大問4「長文読解」
2つ一気に説明しちゃいます。
時間の制限がある中で、長文2つを解かなければなりません。
また、リスニングで強制的に12~15分ほど時間を吸い取られてしまうため
各長文にかけられる時間は15分程度です。
言いたいことはただ一つ、「読むスピードを上げる」。
そのためには、まず自分に足りない力を知るところから始めましょう。
単語→文法→英文の読み方などと英語の勉強には段階があります。
背伸びせず目の前のことからコツコツ取り組むことで、英語の点数が伸びていきます。
また、先ほど紹介した「長文読解講座」は、英文の読み方を徹底指導するので、それまでに単語や文法は復習しておきたいですね!
英作文に関してもGAINは指導してます。
書く→添削→修正を繰り返していくことで確実に点数を上げます!
大問1 リスニング (30点)
大問2 並び替え、適文補充(12点)
大問3 対話文読解 (28点)
大問4 長文読解 (30点)
大きな変更点は特になく、昨年同様の問題構成でした。
では、各大問の分析にまいります!
大問1「リスニング」
リスニングだけで30点も!!!
リスニングというのは不思議なもので、読めても聞き取れないんですよね、、
聞き取れるようにするためには、英語の音声を聞く習慣をつけるしかないです。
GAINの生徒は中3の秋ごろに「長文読解講座」なるものを受講し、読むスピードを上げるだけでなく、聞き取る練習も行います!
また、リスニング教材もあるので、毎日コツコツ積み上げることも可能です!
大問2「並び替え、適文補充」
並ぶ替え問題は英文の構造を理解できているかどうか、つまり文法力を確かめる問題です。
単語だけ覚えていても、太刀打ちできません。
単語とともに文法もきっちり勉強していれば、どのような問題が出ても対応できます!
並び替えが苦手な人は、苦手単元の文法ルールを確認してみて!
大問3「対話文読解」
大問4「長文読解」
2つ一気に説明しちゃいます。
時間の制限がある中で、長文2つを解かなければなりません。
また、リスニングで強制的に12~15分ほど時間を吸い取られてしまうため
各長文にかけられる時間は15分程度です。
言いたいことはただ一つ、「読むスピードを上げる」。
そのためには、まず自分に足りない力を知るところから始めましょう。
単語→文法→英文の読み方などと英語の勉強には段階があります。
背伸びせず目の前のことからコツコツ取り組むことで、英語の点数が伸びていきます。
また、先ほど紹介した「長文読解講座」は、英文の読み方を徹底指導するので、それまでに単語や文法は復習しておきたいですね!
英作文に関してもGAINは指導してます。
書く→添削→修正を繰り返していくことで確実に点数を上げます!
社会
社会の問題構成は以下の通りです。( )は配点です。
大問1 世界地理 (17点)
大問2 歴史 (19点)
大問3 公民 (15点)
大問4 日本地理 (17点)
大問5 歴史 (17点)
大問6 公民 (15点)
出題傾向は例年通りで地理、歴史、公民バランスよく出題されています。
今年の歴史は飛鳥時代から江戸時代初期、明治時代以降が出題されました。
公民は裁判関連、地方自治、労働と財政が出題されていましたね。
問題構成は例年通りとはいえ、石川県の社会の問題は記述がいかんせん多い。
知識だけではなく説明力も同時に求められる問題構成でおよそ配点の半分が説明問題です。
単なる暗記では解けない資料活用問題などもあるので、模試などの実践問題の活用がカギをにぎると思います。
地理の対策として大切なのは、各国、各地方、地域の特色をまとめることです。例えば、気候や地形、農工業です。
それらの知識を活用する問題も出題されています。ノートに地図を書いて特色を色分けでまとめてみると頭に入りやすいかも!
次に歴史ですが、因果関係と時系列の整理が重要です。
歴史資料や模式図から理由や背景を問われる問題が多く出題されています。
また、出来事を時系列順に並べる問題や、同時期に起きた出来事を選択する問題もあるため、単語を覚えるだけではなく
単語同士の結びつきを意識しながら覚えることをおすすめします!
最後に公民ですが、公民は中学3年生になってから習う範囲がほとんどであるため、演習量が他に比べ不足することが想定されます。
そのため、記述対策までもっていくのがかなり難しいです。
そのため、中1,2年の内容に関しては中3になるまでに基礎知識+応用力が身についている状態が望ましいです。
優先順位が低くなりがちですが、何度も何度も模試や過去問をつかって演習を繰り返しましょう!!
大問1 世界地理 (17点)
大問2 歴史 (19点)
大問3 公民 (15点)
大問4 日本地理 (17点)
大問5 歴史 (17点)
大問6 公民 (15点)
出題傾向は例年通りで地理、歴史、公民バランスよく出題されています。
今年の歴史は飛鳥時代から江戸時代初期、明治時代以降が出題されました。
公民は裁判関連、地方自治、労働と財政が出題されていましたね。
問題構成は例年通りとはいえ、石川県の社会の問題は記述がいかんせん多い。
知識だけではなく説明力も同時に求められる問題構成でおよそ配点の半分が説明問題です。
単なる暗記では解けない資料活用問題などもあるので、模試などの実践問題の活用がカギをにぎると思います。
地理の対策として大切なのは、各国、各地方、地域の特色をまとめることです。例えば、気候や地形、農工業です。
それらの知識を活用する問題も出題されています。ノートに地図を書いて特色を色分けでまとめてみると頭に入りやすいかも!
次に歴史ですが、因果関係と時系列の整理が重要です。
歴史資料や模式図から理由や背景を問われる問題が多く出題されています。
また、出来事を時系列順に並べる問題や、同時期に起きた出来事を選択する問題もあるため、単語を覚えるだけではなく
単語同士の結びつきを意識しながら覚えることをおすすめします!
最後に公民ですが、公民は中学3年生になってから習う範囲がほとんどであるため、演習量が他に比べ不足することが想定されます。
そのため、記述対策までもっていくのがかなり難しいです。
そのため、中1,2年の内容に関しては中3になるまでに基礎知識+応用力が身についている状態が望ましいです。
優先順位が低くなりがちですが、何度も何度も模試や過去問をつかって演習を繰り返しましょう!!
数学
数学の問題構成は以下の通りです。( )は配点です。
大問1 小問集合 (30点)
大問2 確率 (10点)
大問3 関数 (13点)
大問4 連立方程式 (10点)
大問5 作図 (8点)
大問6 平面図形 (14点)
大問7 空間図形 (15点)
問題数や問題構成などは例年通りで変更なしでした。
数学攻略のカギは「難しい問題へのこだわりを捨てる」です。
いかにミスなく点数を積み重ねられるかがとっても重要です。
例えば、大問1の小問集合ですが、単純計算、公式の活用、ルートの計算、データ読み取りなど本当に基本的な問題ばかりです。
これだけで30点分も取れるってラッキーじゃないですか???数学の平均点が50点を下回ることを考えたら、大問1で満点をとることがいかに重要かわかりますね。
ただし、「単純計算」を甘く見てはいけません。何度も本番を想定して計算ミスをなくす練習を繰り返しましょう。
また、時間計測を怠らないように意識してほしいです。
数学は問題数や難易度から一番試験時間内に解ききることが難しい教科です。
大問ごとに時間配分を決定して演習をするのが良いです。そして丸つけをするときに、もっと効率よく解けた問題に気づきましょう。
常に時間を意識して、効率を意識して問題を解きましょう!
そしてそして、石川県の数学といえば「図形」!!!
全国的に見ても難易度が高く、完全攻略は難しいといえます。
満点を狙いにいく必要は多くの生徒の場合ないです。
もし、上位校を目指している生徒、数学を得意としている子がいましたら
図形は長期的に学習しなければならないと肝に銘じてください。
一朝一夕では解ける問題ではないため上記に当てはまる人でしたら早めに対策を始めましょう!
大問1 小問集合 (30点)
大問2 確率 (10点)
大問3 関数 (13点)
大問4 連立方程式 (10点)
大問5 作図 (8点)
大問6 平面図形 (14点)
大問7 空間図形 (15点)
問題数や問題構成などは例年通りで変更なしでした。
数学攻略のカギは「難しい問題へのこだわりを捨てる」です。
いかにミスなく点数を積み重ねられるかがとっても重要です。
例えば、大問1の小問集合ですが、単純計算、公式の活用、ルートの計算、データ読み取りなど本当に基本的な問題ばかりです。
これだけで30点分も取れるってラッキーじゃないですか???数学の平均点が50点を下回ることを考えたら、大問1で満点をとることがいかに重要かわかりますね。
ただし、「単純計算」を甘く見てはいけません。何度も本番を想定して計算ミスをなくす練習を繰り返しましょう。
また、時間計測を怠らないように意識してほしいです。
数学は問題数や難易度から一番試験時間内に解ききることが難しい教科です。
大問ごとに時間配分を決定して演習をするのが良いです。そして丸つけをするときに、もっと効率よく解けた問題に気づきましょう。
常に時間を意識して、効率を意識して問題を解きましょう!
そしてそして、石川県の数学といえば「図形」!!!
全国的に見ても難易度が高く、完全攻略は難しいといえます。
満点を狙いにいく必要は多くの生徒の場合ないです。
もし、上位校を目指している生徒、数学を得意としている子がいましたら
図形は長期的に学習しなければならないと肝に銘じてください。
一朝一夕では解ける問題ではないため上記に当てはまる人でしたら早めに対策を始めましょう!
最後に
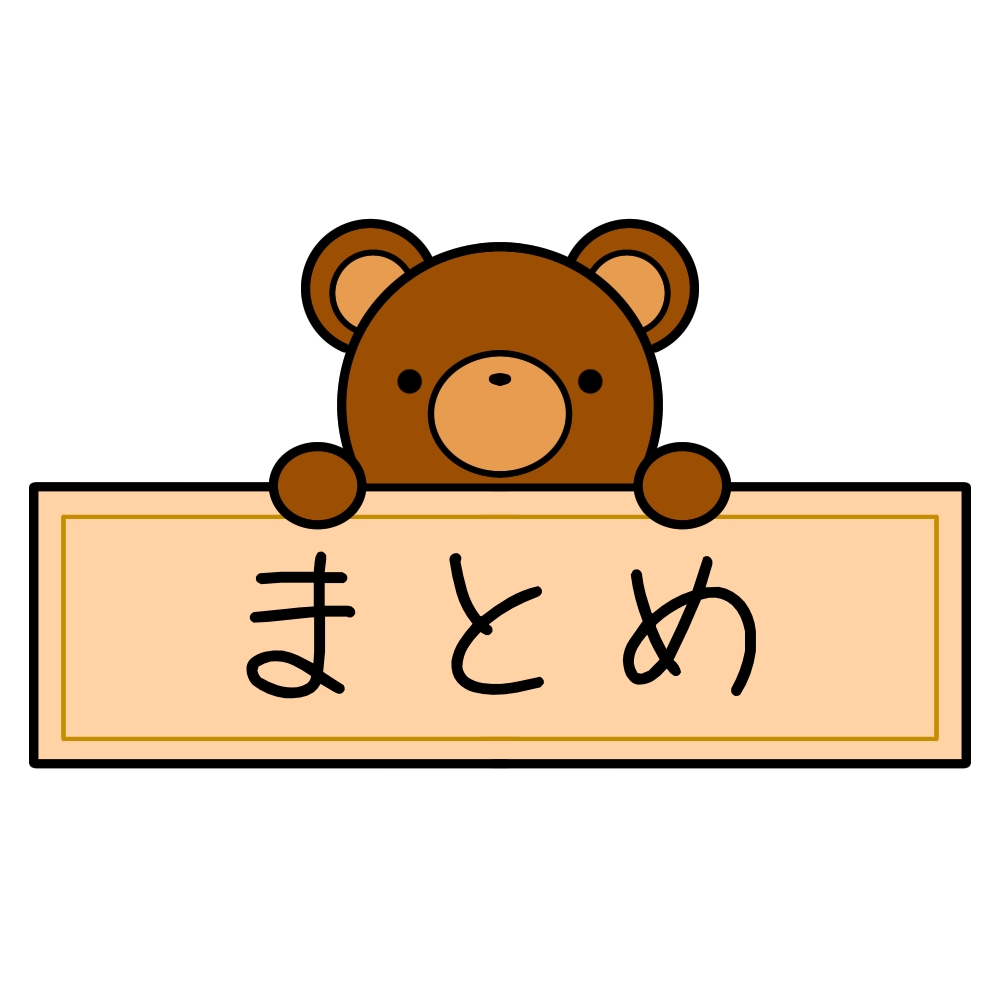
2025年公立高校入試まとめはいかがでしたか?
今年は平均点が10点以上下がりましたが、これは「受験生のレベルが低かった」ということだとは一概に言えません。
そもそも過去数年の平均点と照らし合わせると、近年の入試が難化していることが一目瞭然です。
1990年代の平均点は大体300点前後だったのに対して、2000年代は285点前後、2010年代以降は240~260点となっています。
そのため、入試に対しての情報、知識は常にアップグレードしておかないと危険です
大切なのは、正しい目標設定です。頑張らなさ過ぎてもダメですし、頑張りすぎてもダメということですね。
やみくもに勉強していては点数は取れないため、各教科の目標、そして各単元の目標など細かい戦略がなければ志望校合格は難しいというのが現代の高校入試です。
このように複雑化・難化していく時代の中で志望校合格の道筋を示して一緒に歩むのがGAINの役割です。
ぜひお困りごとあればお気軽にお問合せくださいね!!!
今年は平均点が10点以上下がりましたが、これは「受験生のレベルが低かった」ということだとは一概に言えません。
そもそも過去数年の平均点と照らし合わせると、近年の入試が難化していることが一目瞭然です。
1990年代の平均点は大体300点前後だったのに対して、2000年代は285点前後、2010年代以降は240~260点となっています。
そのため、入試に対しての情報、知識は常にアップグレードしておかないと危険です
大切なのは、正しい目標設定です。頑張らなさ過ぎてもダメですし、頑張りすぎてもダメということですね。
やみくもに勉強していては点数は取れないため、各教科の目標、そして各単元の目標など細かい戦略がなければ志望校合格は難しいというのが現代の高校入試です。
このように複雑化・難化していく時代の中で志望校合格の道筋を示して一緒に歩むのがGAINの役割です。
ぜひお困りごとあればお気軽にお問合せくださいね!!!